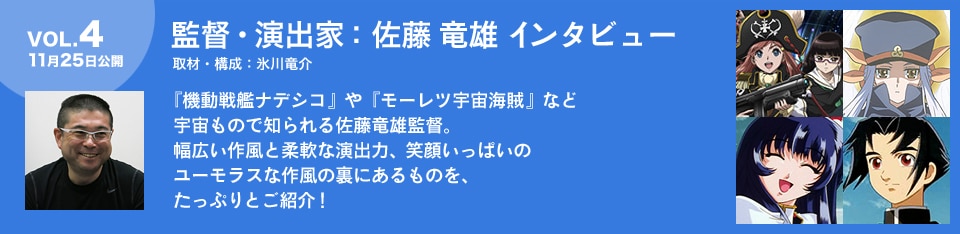――TVの『ナデシコ』のお話をもう少し聞きたいのですが、これから観る方へのガイドなどがありましたら。
- 佐藤
-
 折り返し手前の13話から桜井弘明さんが助監督に入り、そこからフィルムのタッチが明るくなるあたりですね。現場のムードも明るくなったし、作画で和田高明さんが入ってきてギャグ調の表現も入ってきて、「明日の『艦長』は君だ!」(第19話)というルリが歌う回が楽しさのピークでしょう。以後は火星との戦いで重たくなりますし。
折り返し手前の13話から桜井弘明さんが助監督に入り、そこからフィルムのタッチが明るくなるあたりですね。現場のムードも明るくなったし、作画で和田高明さんが入ってきてギャグ調の表現も入ってきて、「明日の『艦長』は君だ!」(第19話)というルリが歌う回が楽しさのピークでしょう。以後は火星との戦いで重たくなりますし。 ゲキガンガー含めて真面目にやっているのかふざけているのか、あの振れ具合が当時は「よく分からない」と言われましたが、十何年経った今では「ナデシコみたいな」と例えられる、ある種ジャンル扱いです(笑)。それだけ生き残れたのは、すごいことだと思います。
ゲキガンガー含めて真面目にやっているのかふざけているのか、あの振れ具合が当時は「よく分からない」と言われましたが、十何年経った今では「ナデシコみたいな」と例えられる、ある種ジャンル扱いです(笑)。それだけ生き残れたのは、すごいことだと思います。
――佐藤さんから見た「ナデシコらしさ」とは?
- 佐藤
-
スカしたやつがいないことでしょう。みんな泥臭いんですよね。誰もが何かしら抱えて生きている。その生っぽいところがいいなと思います。アキトにしても、言っていることとやっていることが違ったりする部分がありますよね。でも「アキトはいいヤツなんだよ」と桜井さんが言った一言に尽きるわけです。そう考えてみると、みんないいヤツじゃないかと(笑)。どこかしらイビツであっても、そこがかわいい。ルリにしても感情表現を知らないだけで、根っこの部分はものすごく人間臭いですから。



――そういうキャラクターの捉え方は亜細亜堂時代からの連綿としたキャリアにつながる部分でしょうか。
- 佐藤
-
まる子の頃、芝山努さん(『ドラえもん』シリーズ監督)に「キャラクターには愛嬌がないとダメだよ」と言われたことがありました。じゃあ、その愛嬌って何だろうと。当時、先輩の女性演出家に「君には女の気持ちが分かっていない!」と言われたことがあって生意気にも反発したりもしましたが、じゃあ分からないなりにどういう形で自分は切りこんでいけばいいのか、ずいぶん考えました。「知らないからできない」ということでは演出家は務まりません。「逃げちゃダメだ」というのは有名な言葉になりましたが(笑)、実にそのとおりだと思います。上っ面ではダメで、食いこんで作品の中に入っていかないと、どこかで無理が出てきてフィルムがフィニッシュまでいかない。作品にしがみつく形で参加する。これって、できそうでできないことなんです。たいてい振り落とされますから。
――『ナデシコ』では個性的なキャラがたくさん出てくるので、入りこむのも大変だったと思います。
- 佐藤
-
描くべきこと描きたいところとスケジュールとの戦いでした。どういう状況でも僕が笑っていられるようになったのは『イサミ』と『ナデシコ』の2本のおかげですね。でも今に至るも、自分なりの方法を模索してばかりなのでいつも苦労しています(笑)。僕の作品が好きな人たちって、「佐藤竜雄のフィルムだから全部観よう」というファンでなく、あれこれ試行錯誤した結果のそれぞれの作品のファンでしょうね。もちろん共通する僕のカラーというものもありますが、こういう特集でもない限り、「えっ、この作品もやってたの?」というタイトルが多いと思います(笑)。