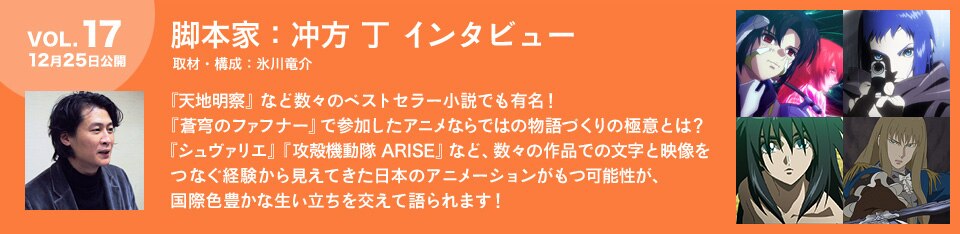――話の順序が前後しますが、そもそも『ファフナー』への参加のきっかけは?
- 冲方
-
僕は小説家としてデビューしたにも関わらず、いろんな業界をウロウロする人間なんです。出版業界が「活字離れ」という流行語の原因を「ゲーム、アニメ、マンガの流行」としていたので、本当かどうか確かめてみようと。それでキングレコードさんともお付き合いが始まったら、ある日突然、大月(俊倫)さんと中西(豪)さんという名物プロデューサーが来て、「放送枠は取れたけど、何をつくるか決まっていない。大急ぎですぐつくってくれ!」と(笑)。そこで「島・群像劇・ロボット」と言われ、当時住んでいた福島に帰る新幹線の中でワーッと書いたのが『ファフナー』の原型になります。「主人公側が全滅してもいいです。むしろそれぐらい激しい方がいい」とも言われ、ずいぶん極端だなと思いましたが、後になってニーズを正確にとらえていたんだと分かり、感心しました。
――最初からものすごい豪速球を投げられていますね。
- 冲方
-
すぐさま投げ返さなきゃと思いました。それで「迷惑だ」と思われるぐらいの分量の設定とプロット26話分書いて送りつけ、「いつまで経っても印刷が終わらないよ」と言われ(笑)。さすがに「どうすればこれをつくれるんだろう?」と困ったようですね。「群像劇」を6家族ぐらいに展開し、三角関係、四角関係、その他あらゆる関係を書き込み、敵のエイリアンにも生命的なものがあったらどうする? など、要素を可能なかぎり詰め込みました。僕自身も初めてだし他にも初めての方が多く、結果的に遠慮なくぶつかり合うことができたのも良かったですね。とにかく時間だけは死ぬほど足らなくて、脚本を一から書き直すことになっても締め切りまで2日しかなく、アフレコ現場から帰りの電車内でプロットをつくり直し、翌朝には提出みたいな修羅場でした(笑)。
――その切迫感ゆえに宿ったものも、ありそうな感じですね。
- 冲方
-
まさに主人公たちの苦しみと自分たちの苦しみが、メチャクチャシンクロしてて、「後がない感」も、お客さんと共有できた感じはすごくありました。
――そこは小説とは違う感覚ですか。
- 冲方
-
やはり集団作業か個人作業かの違いに尽きます。僕にとっては非常に新しい感覚で、アニメーションではAさんとBさんがいるとき、ABができるのではなく、話し合った結果としてのCができるんです。C,D……どうかするとZくらいまで関わるから、何が生まれるか、まるで分からないのが面白い。しかも「監督」とつく人がたくさんいるので、たとえば音響監督の三間(雅文)さんがディレクションで「じゃあこのキャラクター、こっちですか?」なんてこちらに問うてくるたび変化が起きるし、それが一瞬で共有されたりします。変化球で演じたつもりが、むしろそのキャラクターの本質を突いてると分かったりして、「こういう風にコイツは命を燃やすのか」というのが見えてしまい、そのせいで早死にするキャラが出るわけです(笑)。
――アニメの現場で、そうしたライブ感覚は大事ですよね。
- 冲方
-
最初は試行錯誤の期間もありました。方向性が見えてきたのは7~8話ぐらいでしょうか。そこからはもう、みんなの突っ走りっぷりがすごかったですね。『ファフナー』の新企画が立ち上がるたびに、「またやるの!? キツイなー」って思いますからね(笑)。作中の言葉が制作現場の共有フレーズになることも多くて、「消耗戦だー!」とか「痛みは祝福ですから」とか、スタッフも真顔で言い始めますし。それだけ全員がのめりこめる作品に参加できるのは、非常に幸せなことです。
――小説と違うところは、他にどんなことがありますか?
- 冲方
-
それは「耳で言葉を聞くこと」ですね。小説は目で文字を読みますが、アニメは音声と映像でとらえる。各自のリアルタイムで解釈されます。セリフを勘違いされると、その人の中ではそのまま進行してしまい、まるで違う解釈が生まれる場合が多いんです。逆にそこから新しいキーフレーズが誕生したりもするので、非常に不定形でもあり、だからこそ躍動感が生まれるのかなと。小説の読者は「作者の意図を読み取ろう」みたいな気持ちの方も多いですし、50音しかない記号ですべての意味をとらえる活字は、あらゆる媒体の中で一番デジタルなんです。それだけ想像の余地があり、行間、文間を読もうとする性質がつよいんですね。映像や音楽はアナログですから、できあがったものがすべてで、後はどんな解釈があり得るか? という方向にいく。お互い入れ子の関係です。
――なるほど。ご自身が活字で書かれたものが、実際に映像化されたときの驚きもあったでしょうか?
- 冲方
-

 『ファフナー』ではルガーランスという設定を考えたとき、「どんな絵になるのかな?」と思いましたが、非常にうまくいきました。代表的な武器のポジションになれたのも、ひとえにビジュアルの力ですね。フェストゥムにしても金色を使いまくったのは、僕がアニメーションで苦手な色だというのを知らなかったからですけど(笑)。
『ファフナー』ではルガーランスという設定を考えたとき、「どんな絵になるのかな?」と思いましたが、非常にうまくいきました。代表的な武器のポジションになれたのも、ひとえにビジュアルの力ですね。フェストゥムにしても金色を使いまくったのは、僕がアニメーションで苦手な色だというのを知らなかったからですけど(笑)。
――あの発光や映り込みは、デジタルでなければ難しいと思います。
- 冲方
-
僕としては「美しい敵」ということだったんですが、美しさもどんどんバージョンアップして金色の塗り分けも数が増え、金属とも陶器ともつかない処理に進化して、すごいですよね。小説だと描写すればするほど分かりづらくなるのが、映像はいったんお客さんと共有できれば、もっともっと突っ走ることができる。そこは強みです。
――羽原信義監督とのお仕事はいかがですか?
- 冲方
-
本当に優しくて熱心で、すごく柔和な音頭をとる方です。基本的に絵の世界の方で、深い愛情を持っていると感じます。愛情はたいがいぶつかり合うものですから、音響的な愛情と絵的な愛情と脚本的な愛情が衝突する中から、いつも何かが生まれる。その意味で非常にいい現場です。もちろん平井(久司)さんも能戸(隆)さんも含め、すべて作品づくりに関わってる方は、全力でぶつかっている感じです。だから10年経っても、前と同じような大変なことをできるんだなと。
――すでにイベントで先行上映されましたが、その手応えは?
- 冲方
-
客席でお客さんといっしょの空気を味わえたのが、ものすごく良かったです。笑ってほしいところで笑ってくれるし、ビックリしてほしいところでビックリしてくれる。長年のお付き合いで互いに楽しみどころを、大変よくわかっているような一体感がありましたね。ぜひお楽しみください。
――さてこの連載ではアニメ原体験もうかがっているのですが、冲方さんの場合は幼少時に海外在住(シンガポール、ネパール)だったそうで、独特の体験をお持ちかと。日本のアニメや漫画には、どのように触れてましたか?
- 冲方
-
すでに日本の作品は世界的に評価され始めていたので、『AKIRA』を最初に知ったのも先生が読んでいる英字新聞なんです。「AKIRAってどういう意味?」って聞かれ、「人の名前だ」「どんな意味?」「えっと、シャイニングみたいな感じかな」みたいな会話があって、僕にとっても日本のものが海外の学校で話題になることに、ものすごいインパクトを感じました。他にも『風の谷のナウシカ』や『機動戦士ガンダム』など断片的に情報が入ってはくるものの、つじつまが全然合わない。なにしろ「少年ジャンプ」一冊手に入れるのに8000円くらいかかる時代ですし、VHSテープでアニメを手にいれても、まだ吹き替えや翻訳はほとんどないので、ドイツ人やアメリカ人、韓国人、エジプト人の同級生が「訳してくれ」と言ってくるんですね。
――単に海外というだけでなく、ものすごく多国籍な感じですね。
- 冲方
-
インターナショナル・スクールだったので、1クラス30人の全員人種が違ったりしました。宗教観も違うから、解釈も違ってくるんです。たとえば『ガンダム』では「連邦軍とジオン軍、どっちがキリスト教徒?」と聞かれたりしました。ベースとなる常識が違うんです。『AKIRA』でも片方はテツオで片方がカネダ、ファーストネームとファミリーネームが混在していることが、通じないんです。お互いの解釈や理解のベースがゼロのところから僕が訳すことで、コミュニケーションのきっかけができる。僕が好きなものはドイツ人やエジプト人やイラン人も好きだったりするし、『ドラえもん』をバングラディシュ人が面白いと言ってくれたりする。娯楽だけでなく、僕自身の訓練にもなっていたと思いますね。
――面白いですね。『ファフナー』のテーマにもつながっている感じで。
- 冲方
-
コミュニケーションという点では、まさにそうです。もっとも難しかったのが食事で、宗教的に禁止されている食事をしているキャラクターには絶対に感情移入できないんです。当時の思い出話はキリがないですが、予想もしない解釈がポンポン飛び出るのも面白かったですね。『ドラえもん』をアルファベット化すると、ドリームマン(Dreamman)の綴り替えに近くなるので、みんなで「ドリームマン、ドリームマン」と呼んでみたり。ものの見方は一方向である必要はない。そういうイメージの発展があるという点では、僕の中で大事な原体験です。
――そして小説を書こうと思われたのは、どんなきっかけでしたか?
- 冲方
-
漫画やアニメーションからたくさんのものを得たので、翻訳する必要のないもの、ダイレクトに伝わるものに憧れて、最初は絵の世界に行きたいと思っていました。そこで絵の勉強をして高校時代は美術部の部長もやりましたが、展覧会をやるのに部長の僕が一枚も描けない。先生に催促されたとき、はたと気づいたんです。「これから描く絵がなんであるか」という文章を、僕はずっと書いてたんです。そこで「アレ!?」と(笑)。漫画の練習をしても、文字だらけの吹き出しがどんどんデカくなり、絵を描く場所がなくなったり。自分の憧れと特質って全然ちがうものなんだと気づき、それで高校卒業時に書いた作品で小説デビューすることになるわけです。
―やはり文字と絵を往復した時期があったということですね。
- 冲方
-
絵が苦手とするものにも気づきました。たとえば人間関係をどう表現するか。ズラッと人を並べたとき、誰がお父さんで誰がお母さんか、何となく似ているぐらいで伝えるのは至難の業でしょう。ましてや機微や不和、コミュニケーションの部分をどうすれば表現できるか……などと試行錯誤しているうちに、文章へ行ってしまったわけです。
――『マルドゥック・スクランブル』でSFというジャンルを選ばれたのは?
- 冲方
-
1996年、97年ぐらいはまだライトノベルという言葉も定着してなくて、「小説の帯にSFと書くと売れない」とか言われ、SFが冷遇されていた印象がありました。天邪鬼なのか、「だったら狙い目じゃないか」と、かえってやりたくなり(笑)。「アメリカン・コミック調の感じで隆慶一郎っぽく」みたいな発想で、架空の都市で起きる犯罪ものを50枚の予定で書き始めたら、長編になってしまったというわけです。
――押井守監督の『GHOST IN THE SHELL 攻殻機動隊』がアメリカでヒットした時代(米国ヒットは1996年)ですが、その時期から意識はされていましたか?
- 冲方
-
 みんなが勇気をもらえた作品でした。その後のリアリティをだいぶ変えたと思います。発表する前の『マルドゥック・スクランブル』でも「銃撃戦の最中に飛んだり跳ねたりするアクションはリアリティがない」と批判されたんですが、『攻殻機動隊』を経て『マトリックス』が大ヒットした途端、みんな飛ぶようになりましたよね(笑)。「女の子のパートナーがネズミは可愛くない」とも言われましたが、『スチュアート・リトル』が公開されたとたん、言われなくなり(笑)。ですからリアリティって現実はあまり関係なく、フィクションとしての共通了解がどうかだけなんです。誰かが風穴開けると、その瞬間ガラッと変わるものですね。
みんなが勇気をもらえた作品でした。その後のリアリティをだいぶ変えたと思います。発表する前の『マルドゥック・スクランブル』でも「銃撃戦の最中に飛んだり跳ねたりするアクションはリアリティがない」と批判されたんですが、『攻殻機動隊』を経て『マトリックス』が大ヒットした途端、みんな飛ぶようになりましたよね(笑)。「女の子のパートナーがネズミは可愛くない」とも言われましたが、『スチュアート・リトル』が公開されたとたん、言われなくなり(笑)。ですからリアリティって現実はあまり関係なく、フィクションとしての共通了解がどうかだけなんです。誰かが風穴開けると、その瞬間ガラッと変わるものですね。