――自殺した高校生が転生し、人生をやりなおすというシリアスな物語をアニメーションで描いた青春映画『カラフル』が2011年に公開され、文化庁メディア芸術祭アニメーション部門大賞ほかいろんな賞を受賞されました。2年前には木下惠介監督の若き日の出来事を描いた映画『はじまりのみち』を実写で撮られ、これも大きな評判を呼んでいます。そして今回の『百日紅~Miss HOKUSAI~』では江戸時代の浮世絵師を描いています。その企画のきっかけは何だったのでしょうか。
- 原
-
 『カラフル』の後、その次の作品の企画に取りかかったものの、なかなか具体的に決まらなかったんです。僕もちょっと困ったことになったなと思い始めたときに、古くからの知り合いであるProduction I.Gの石川(光久)さんのところに営業に行ったわけです(笑)。それで「たとえばこんな作品がつくれれば、僕は嬉しいんだけど」というサンプルとして渡してきたのが、杉浦日向子さんの漫画作品だったんですね。
『カラフル』の後、その次の作品の企画に取りかかったものの、なかなか具体的に決まらなかったんです。僕もちょっと困ったことになったなと思い始めたときに、古くからの知り合いであるProduction I.Gの石川(光久)さんのところに営業に行ったわけです(笑)。それで「たとえばこんな作品がつくれれば、僕は嬉しいんだけど」というサンプルとして渡してきたのが、杉浦日向子さんの漫画作品だったんですね。
――なるほど、最初は違う杉浦作品だったわけですか。
- 原
-
そうしたら石川さんが「杉浦さんなら『百日紅』をうち(I.G)で企画を動かしたことがあったんだよね、あきらめたんだけどさ」と言うわけです。それでしばらくして今度は石川さんから呼ばれて行ったら、その場で「原さん、『百日紅』をやらないか」と言われて。「ただし、予算はこれこれ。尺は90分以下」というのが条件でした。
――それで腑に落ちました。広報資料では「ご縁があって」という書き方になっていて、「あれ? 原監督から出した企画ではないのかな」と首をひねっていたんです。杉浦作品の提案がきっかけだったのなら、これはまさに「ご縁」ですね。
- 原
-
そういうことなんですよ。
――それで、実際に動き出したのはいつごろでしょうか。
- 原
-
ちょうど『はじまりのみち』と同じぐらいからスタートしたので、実写の方が終わるまでI.Gさんにずっと待ってもらい、それから絵コンテ作業に入ったという感じです。
――直前が実写ということで、その経験が活きた部分はありますか?
- 原
-
むしろ「逆に活きた」というのはあるかな。実際に『はじまりのみち』を終えて、久しぶりにアニメの絵コンテを描き始めたとき、本当にうんざりしてしまったんですよ。
――うんざり? 何にですか。
- 原
-
実写ってカメラがあって役者さんがいて、美術があるかもしくは景色があって、監督が「よーい、はい!」と言って役者さんがいい演技をして、監督が「カット!」と言って、「オーケー!」と言ったら、もうそれでシーンが完成しちゃうわけです。そのスピード感に比べて、アニメーションづくりの工程の面倒くささと言ったら(笑)。「またこの白いコマを全部埋めていかないといけないのか」と思ったら、うんざりしたんです。それで本当に最初は全然やる気にならなかった。
――実写には、制作期間が短い新鮮さがあったってことですか。
- 原
-
はい。
――生の被写体を撮るって部分はどうですか?
- 原
-
そうですね。実写は早い分、アニメーションづくりでは感じたことのないような緊張感とかプレッシャーは、やっぱり相当ありましたよ。
――アニメだったら後でいくらでも直せるのに?
- 原
-
そうそう、そうなんですよ。だからこそ、今回はアニメでしかできないことをやろうとしました。特に画づくりとかは、挑戦していますね。
――原作『百日紅』は、葛飾北斎を中心に江戸の風物や町人の感覚を描いた点で、非常に世評の高い作品です。まず原監督は、どんな感じで杉浦日向子という作家と出逢われたのでしょうか。
- 原
-
 20代の後半のころ、初めて杉浦さんの作品を読みました。それは『風流江戸雀』という作品で(1987年単行本化、文藝春秋漫画賞受賞)、それを見たとき、ものすごく面白かったし、新鮮に感じたんです。そこから杉浦さんの作品を、本当に手に入るものというか出ているものは全部という感じで、買って読み始めたのがきっかけですね。
20代の後半のころ、初めて杉浦さんの作品を読みました。それは『風流江戸雀』という作品で(1987年単行本化、文藝春秋漫画賞受賞)、それを見たとき、ものすごく面白かったし、新鮮に感じたんです。そこから杉浦さんの作品を、本当に手に入るものというか出ているものは全部という感じで、買って読み始めたのがきっかけですね。
――最初からものすごく惹かれるところがあった。それは、どんなところに?
- 原
-
まずは、やっぱり杉浦さんという作家の演出力のすごさ。そこに引かれましたね。
――杉浦さんは1993年に漫画家を引退し、江戸研究家として一世を風靡しますが、ただ単に江戸に詳しいという知識面ではなく、絵としての見せ方だったと。
- 原
-
ええ。同じ演出をする人間として、なんて憎い人だろうと(笑)。自然体でありながら、実に奥深いものをサラリと伝えてくる。年齢も杉浦さんは僕の1歳上なので、ほとんど同年代なのに、なんでこんなことができちゃうんだろう? そんな嫉妬です。
――『百日紅』は1983年から1987年まで連載とのことですが、原監督が20代後半で出逢われたなら、ちょうど連載中では?
- 原
-
たぶん……ですが、僕が杉浦さんのことが気になり始めたとき、すでに『百日紅』も2巻ぐらい出ていて、それで読んだんだと思います。
――当時初出の単行本は全3巻ですよね。しかも、今読めるものとは構成が違ってて、文庫で初収録のエピソードがあると。
- 原
-
単行本のときには、3巻の最後が『野分(のわき)』だったんです。つまりお猶のエピソードで締めている。そこで作品が終わった印象が、僕としてはすごく強かったので、映画にすることが決まったときも、「あのエピソードをクライマックスに持ってこよう」と、まず思ったんです。あとはそれをクライマックスにするためには、お栄とお猶という姉妹を縦軸で描いていくのがいいだろうと。それで、ああいう構成にしています。
――なるほど、原作は短編集ですから、オムニバス風に見せつつも映画としては一本に通したものが必要と。お猶は病弱で目が見えない妹という存在です。
- 原
-
原作では、お猶は『野分』にしか登場しないんです。
――手前の船遊びや雪遊びの部分は、姉妹を描くためのオリジナルでしょうか。
- 原
-
ええ。
――そんな楽しい時間を過ごしたとはいえ、はかない感じ含めて死が今よりも自然に描かれていますよね。
- 原
-
死が非常に身近にあるということ。その部分は、杉浦さんの他の作品を見てもよく描かれていることなんです。だから、それはやっぱり大事にしようと思いましたね。今の人たちより死は特別なものじゃない。そんな意識はみんなが持ちながら生きていたんじゃないかなって気はしますけどね。
――かなり小さいうちに死んじゃう子もいる。そうした部分を価値観の違う現代の観客に、どう伝えようと思われましたか。
- 原
-
うーん……。いつの時代でも、それぞれの人の運命ってものはあると思うんです。だから、彼女だけがことさら不幸だという描き方だけは、あまりしたくないなとは思いました。子どものころに死んじゃう人は死んじゃうし、長生きする人は長生きする。実際、北斎の方は90歳まで生きたわけですから。
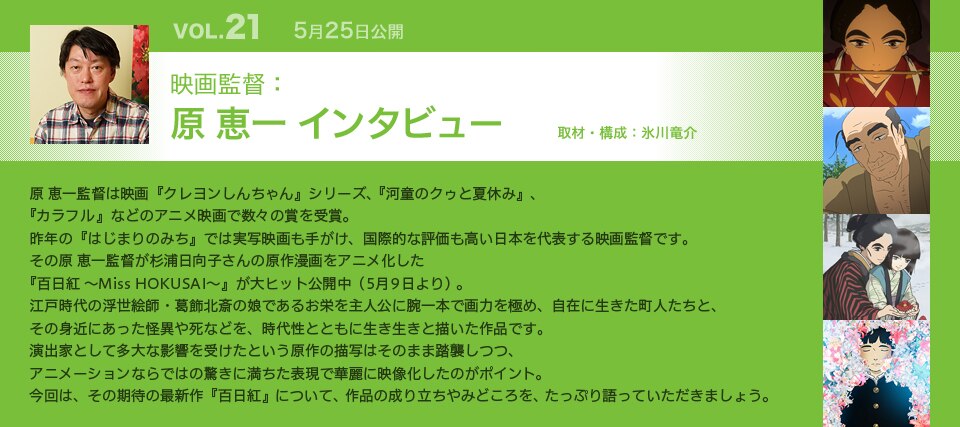


 20代の後半のころ、初めて杉浦さんの作品を読みました。それは『風流江戸雀』という作品で(1987年単行本化、文藝春秋漫画賞受賞)、それを見たとき、ものすごく面白かったし、新鮮に感じたんです。そこから杉浦さんの作品を、本当に手に入るものというか出ているものは全部という感じで、買って読み始めたのがきっかけですね。
20代の後半のころ、初めて杉浦さんの作品を読みました。それは『風流江戸雀』という作品で(1987年単行本化、文藝春秋漫画賞受賞)、それを見たとき、ものすごく面白かったし、新鮮に感じたんです。そこから杉浦さんの作品を、本当に手に入るものというか出ているものは全部という感じで、買って読み始めたのがきっかけですね。

