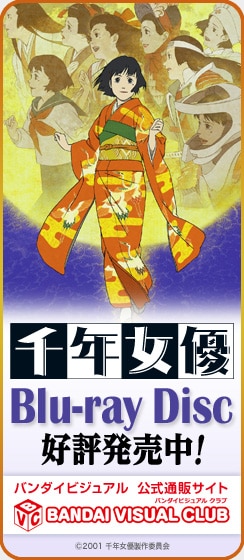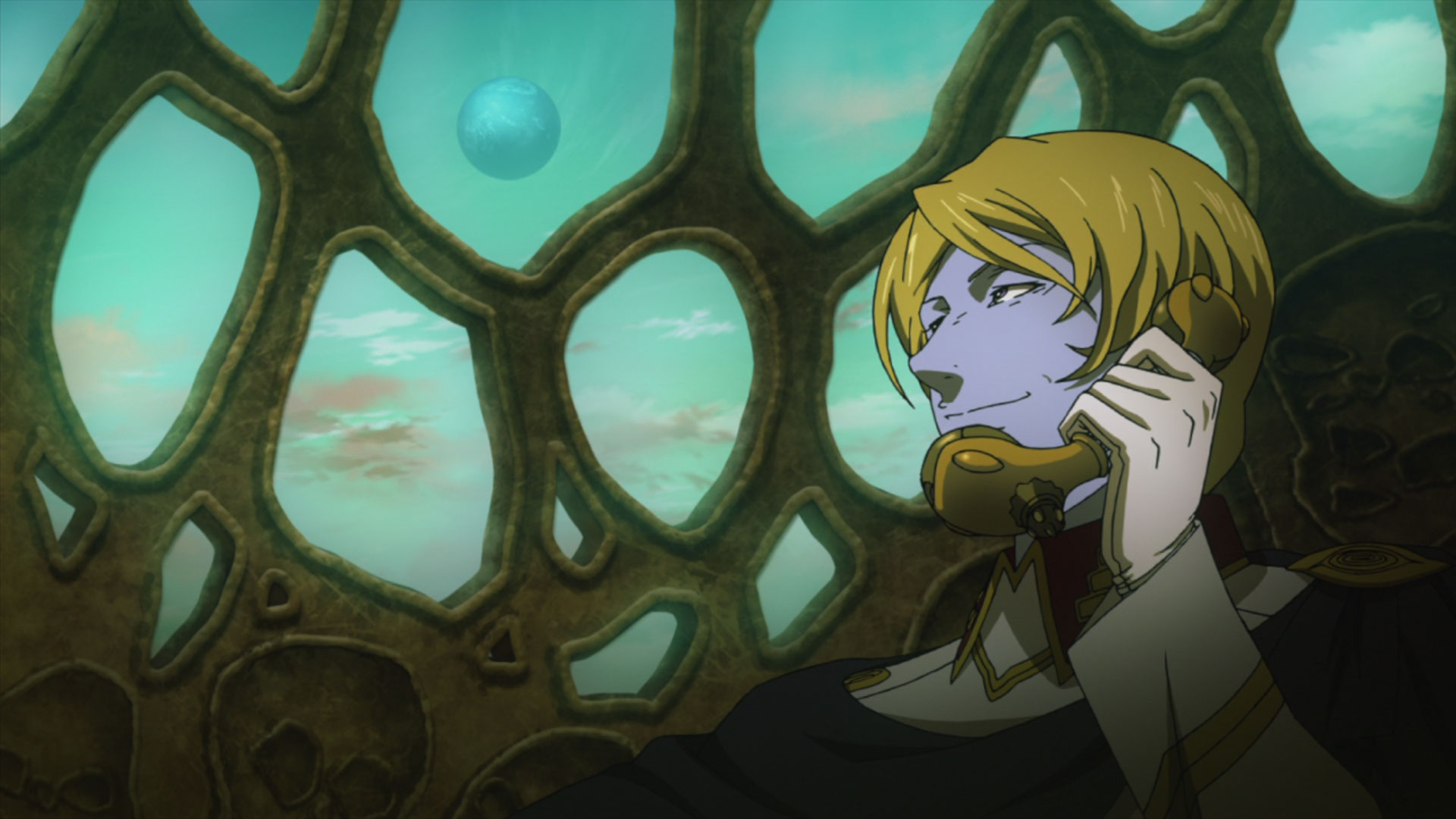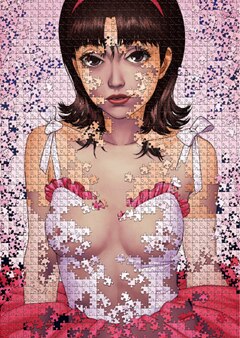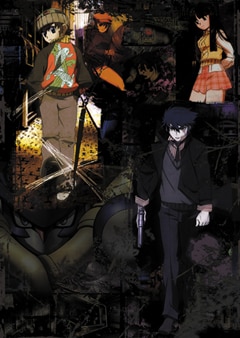――各話担当で参加されたTVシリーズについても
うかがいたいです。『
夏色キセキ』(12)はいかがでしたか。
- 村井
-
シリーズ構成の浦畑(達彦)さんに誘われたのがきっかけで、「ジュブナイルっぽい雰囲気にしたい」と言われました。少女4人がひと夏の経験を経て、ちょっぴり成長する物語です。この作品では下田へロケハンに行きました。山と海と港が近く、それぞれ歩いて行けるような距離感で、コンパクトにまとまった良い土地です。
――ご自身の担当回でオススメは?
- 村井
-
 子ども時代と中学生時代が混交していく第10話は気に入っているので、ぜひ観てください。「タイムトリップ」を描く場合、「現在から過去へ飛ぶ」とすることが多いと思います。でもこの回では、過去の子どもが現在へタイムスリップする。シリーズ中の役割としてもジュブナイルとしても、それで良い方向に落ち着かせることができました。浦畑さん担当の最終回もすごい脚本です。ボリューム感があってまとめにくいお話を力技でねじ伏せ、なおかつジーンとさせてくれます。
子ども時代と中学生時代が混交していく第10話は気に入っているので、ぜひ観てください。「タイムトリップ」を描く場合、「現在から過去へ飛ぶ」とすることが多いと思います。でもこの回では、過去の子どもが現在へタイムスリップする。シリーズ中の役割としてもジュブナイルとしても、それで良い方向に落ち着かせることができました。浦畑さん担当の最終回もすごい脚本です。ボリューム感があってまとめにくいお話を力技でねじ伏せ、なおかつジーンとさせてくれます。

- 村井
-
これは主張しておきたいことですが、もともと僕は「旧作どおりにやろう派」だったんです。なので、第8話(星に願いを)は旧作の3話分に相当する物語をできるだけ旧作っぽくひとつにまとめました。でも、出渕裕総監督のアイデアもあってかなりうまくいったと感じる一方、「全編を旧作どおりにするのはムリだな」とも思ったんです。旧作を観直すと、あの時代だからこそ許された脚本だと実感したんです、今の視聴者だと、絶対に許してくれない。しかもその後、僕には旧作どおりの話はまったく来なくなってしまって(笑)。
――てっきりサイコサスペンスが得意だから立候補したのかと。
- 村井
-
 違います、出渕総監督が僕にそういう回を振るからです(笑)。第14話(魔女はささやく)にしても……。
違います、出渕総監督が僕にそういう回を振るからです(笑)。第14話(魔女はささやく)にしても……。
――あれは「実相寺(昭雄)回」ですよね。「第四惑星の悪夢」(『
ウルトラセブン』第43話)みたいな。
- 村井
-
そうなんです。もともとは出渕さんがやりたかったことで、「ここに電話機が置いてあってさ」と言われるので、「ハイハイ、分かりました」と(笑)。そんな特殊な回でしたが、演出に力を入れてくれて良かったです。
――ビッグタイトルですが、心がけたことは何でしょうか?
- 村井
-
やはりスタッフ一同の「旧作を大切にしよう」というコンセンサスですよね。それが『宇宙戦艦ヤマト』をリニューアルする方法として、一番の正解だろうと。その前提で、当時の子どもでも気づいた矛盾点は解消して現代に放送できるかたちにする。ガミラス語を言語学者の大堀壽夫先生が監修し、サイエンスライターの鹿野司さんもSF考証で参加して、厚みを出しています。脚本も土台を守りつつ現代に成り立たせようと、打ち合わせも毎週8時間くらいやり続けましたし、毎回5~6稿は重ねています。


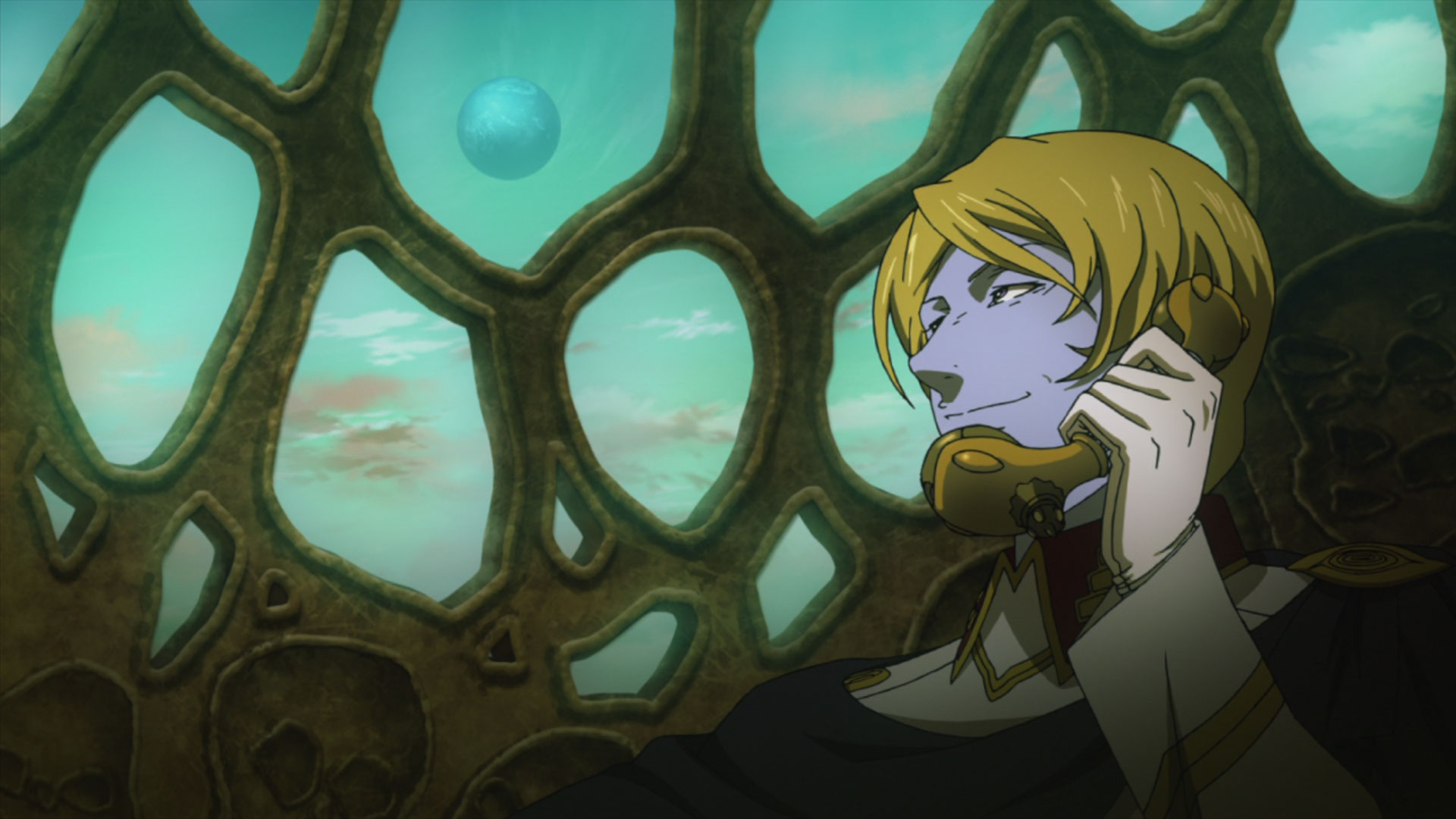
――手応えはいかがでしたか?
- 村井
-
つくっている最中は必ず叩かれるという予感がして、「勝ち戦ではないが、骨を残そう」という悲壮感をいだきつつ書いていました。でも、ものすごくクオリティの高い映像にしていただけたおかげで、お客さんにも好意的に受け止めていただけて、今は感謝の気持ちでいっぱいです。

――さて4月からの最新作『シドニアの騎士』についても、お聞かせください。『
ヤマト2199』と同様に引き続き、こちらも「宇宙SF」です。
- 村井
-
近年の「宇宙SF」では太陽系内の話が多くなっていますが、もっと壮大な舞台で物語が展開します。そしてスペースオペラの『ヤマト』ともテイストが違い、弐瓶勉さんならではの独特な世界観なので、まずそれを大切にしようと。敵の奇居子(ガウナ)は弐瓶ワールド共通の存在ですが、それをいかにインパクトを与えつつお客さんに提示できるかを最初に考えました。
――その奇居子を迎撃する存在として、巨大ロボットも登場します。
- 村井
-
フカンで見ると「ロボット対怪獣」という構造でして、日本の漫画で『パシフィック・リム』(13)より先にやっていたわけですよ! それと人間関係が豊かに描かれているので、いかにこうした要素を融合させて映像化するかが大きな課題でした。漫画の方は弐瓶さん特有の「文法」で描かれているので、何度か読み返すことで初めて真意が見えてくる部分もあります。ページを戻せない映像では、それをいかに的確に伝えられるかが勝負ですね。たとえば最初の数話では、物語の構成を少し原作と変えつつ、でも原作ファンが観たときに「原作どおりだ」と思えるような工夫をしています。
――壮大なストーリーですから、全体を構成するのも苦労されたのでは?
- 村井
-
 原作のどこを切り取るか、どこまでストーリーを進めるかは、たしかに難しかったです。というのは今回はCGを多用するので、その作業の進行度合いとの兼ねあいもあるからなんです。1年以上前から準備を進めていますが、CGのためのスケジュールが間に合わない部分も出てきて、削る必要がでてきました。
原作のどこを切り取るか、どこまでストーリーを進めるかは、たしかに難しかったです。というのは今回はCGを多用するので、その作業の進行度合いとの兼ねあいもあるからなんです。1年以上前から準備を進めていますが、CGのためのスケジュールが間に合わない部分も出てきて、削る必要がでてきました。 その一方で、CGでは一度モデルをつくったら繰り返し使えるので、逆に可能となったことも多いです。
その一方で、CGでは一度モデルをつくったら繰り返し使えるので、逆に可能となったことも多いです。
そんなバランスを見ながら進めたシリーズです。特に今回アニメーション制作を担当したポリゴン・ピクチュアズさんとしては「動きで見せたい」と考えられたので、脚本段階では「TVシリーズでできるのかな?」と心配しつつ、アクションを書きました。結果的に、本当にビックリするような映像が上がっています。ギレルモ・デル・トロ氏にぜひ見て欲しい(笑)。
――脚本を書かれる立場として、何か違いは感じられましたか?
- 村井
-
2Dアニメの場合、絵コンテや演出でうまくカットしたり押し込んだりしてテンポをあげるし、むしろ「脚本が短いと困る」と言われるくらいなので、長めに書きます。ところがCGだと実写に近づき、尺が長くなりがちなんですね。脚本家としてはなるべく要素を多く詰め込みたい思いもあったので、このバランスも大変でした(笑)。その葛藤は最終回付近まで続きましたね。
――殺伐とした世界観の中に、しっとりとした描写もある作品です。
- 村井
-

 キャラクターに親近感を持ってもらうこと、キャラクター同士の関係性を描くことは大事にしてますね。監督の静野(孔文)さんもていねいに心理を演出される方で、脚本でキャラクターを飛ばし気味に書いた部分に、少しセリフを積んだりしています。見せ場のひとつになる「重力祭り」を描くために浴衣も新規でモデリングするなど、スタッフが死守してくれた部分は多いですね。
キャラクターに親近感を持ってもらうこと、キャラクター同士の関係性を描くことは大事にしてますね。監督の静野(孔文)さんもていねいに心理を演出される方で、脚本でキャラクターを飛ばし気味に書いた部分に、少しセリフを積んだりしています。見せ場のひとつになる「重力祭り」を描くために浴衣も新規でモデリングするなど、スタッフが死守してくれた部分は多いですね。
――そんな独特の物語世界を表現するためには、どんなことに留意されましたか?
- 村井
-
 居住塔があって街があるというロケーションと生活感を大切にしたいと思いました。特に土地の高低差には気をつけましたね。人間が移動するシーンでも「この世界には高さがある」ということを意識して書いています。
居住塔があって街があるというロケーションと生活感を大切にしたいと思いました。特に土地の高低差には気をつけましたね。人間が移動するシーンでも「この世界には高さがある」ということを意識して書いています。
――3D的なカメラワークも活かせますね。
- 村井
-
あがった映像を観て、驚きました。メカが動くことは分かっていましたが、キャラクターがこれだけ演技できるということに、新鮮味があります。
――今回はプレスコ(画に先行して声を収録する手法)を採用しているそうですが。
- 村井
-
それも演技優先にするためです。声のニュアンスに基づいて、CGキャラクターを動かすわけです。原作者の弐瓶さんも私も毎回プレスコに参加しているので、収録現場でセリフを修正できるのは大きなメリットでした。弐瓶さんはホン打ち(脚本打ち合わせ)にも毎回出席し、漫画とアニメの差で脚本上変わる部分を理解していただいた上で、さらに新しいアイデアも出されるんです。本当に感謝していますし、原作ファンにも満足していただけるんじゃないかと期待しています。
――最後に、まとめの言葉をいただけますか?
- 村井
-
世界で初、他に類をみない映像になっていますので、ご覧になって損がない作品だと思います。日本のアニメーションは、世界でトップクラスの映像作家たちがつくっていることが伝わるでしょう。脚本家になって一番感謝していることは、そんな画期的な映像が誕生する現場に何度も立ちえたことですね。だから僕はきっと、日本でキャメロンに一番近いところの仕事をさせて貰ってきたんじゃないかなって思ってます(笑)。

 脚本家:村井 さだゆき インタビュー
脚本家:村井 さだゆき インタビュー


 村井 さだゆき(むらい・さだゆき)
村井 さだゆき(むらい・さだゆき)