|
モビルスーツ戦と音楽の見せ場
――今後のみどころがあれば、教えていただけますか?
- 松尾
 第6話以後は戦闘のバリエーションですね。シチュエーションが空中だったり密林だったり海だったり、逐一変わっていくので、こういう場所だからこう戦わざるを得ない、みたいな部分がモビルスーツ戦のみどころだと思います。いきなり広い場所になったりするのは避けたいので、南洋同盟とは密林のせせこましいところで戦います。アッガイは全部で6機出てきますが、玄馬(宣彦)さんが「装備を変えたほうがいい」というので、レーダー、重火器、格闘用みたいな感じで分けて設定しています。今までのイメージとも変わるし、アニメ版ならではのみどころになると思います。 第6話以後は戦闘のバリエーションですね。シチュエーションが空中だったり密林だったり海だったり、逐一変わっていくので、こういう場所だからこう戦わざるを得ない、みたいな部分がモビルスーツ戦のみどころだと思います。いきなり広い場所になったりするのは避けたいので、南洋同盟とは密林のせせこましいところで戦います。アッガイは全部で6機出てきますが、玄馬(宣彦)さんが「装備を変えたほうがいい」というので、レーダー、重火器、格闘用みたいな感じで分けて設定しています。今までのイメージとも変わるし、アニメ版ならではのみどころになると思います。
音楽では新キャラクターのビアンカがピアノを弾くので、イオとのセッションを楽しんでいただければと。前回イオがコックピットでスティックを振ってましたが、今回は本物のドラムとピアノを弾くシーンがあります。ライブを狭い部屋でやるので、パイロットたちが息抜きできてるような部分も見せ場になってくれると思います。他にもみどころは非常にたくさんありますね。
――ところで、監督が考えるマンガとアニメの違いは何でしょうか? あるいはアニメ化するとき気をつけてることは?
- 松尾
- ページをめくってとか、このコマを大きくしてとか、読者側のペースでは見せられないということに尽きますね。映像は同じフレームの中でつながっていて、作り手側の考える間で見せていくので、そこが最大の違いです。マンガではこうしているけど、映像ではこうしたほうが見栄えが良くなる。そんなことを、延々考えながらやっていますね。「こういう題材なら実写ではどうですか」みたいなことをよく言われますが、絵でつくりたいんです。マンガもアニメもどちらも絵ですが、アニメのほうが動かせるし音もつけられるし、きっと豪華に見えるでしょう。じっくり読めるマンガと、作り手のタイミングで見せるアニメと。基本的に僕らは後出しジャンケンだから、プラスアルファできる要素はたくさんあると思っています。それをうまく使おうと工夫していますね。
――小形尚弘プロデューサーの談話で、松尾監督を選んだ理由は、空間をつくるのがうまいと語られていたんですが、いかがですか。
- 松尾
- 自分では無意識ですね。ただ「人のいる空間」はいつも意識しています。昔の工場はみんなグレーでしたが、今は手すりを赤くしたり、フロアによって色を分けたりしています。地下街や大きめの駐車場でも、人の動線を分かりやすく作っている。そんな部分をなるべく取り入れています。
――日常生活の中にヒントがあるということでしょうか。
- 松尾
- 今さん(今 敏監督)が言ってた「みんな当たり前に見えてるものが描かれていないのはイヤだ」という言葉がすごく記憶に残ってて、ホントにそうだと思うんです。当たり前に接しているものがあると、自分たちの生活空間の延長として見てもらえるんじゃないかなと。それをやっておくとシンパシーを得られて、キャラクターとの距離感が縮むと考えているんですね。セリフにしても、どうでもいいようなセリフや会話を足したりします。そうすることで人の関係値が変わり、より親近感がわいてくれるだろうと。アニメはそもそもセリフが大仰ですから。マンガで言えば、吹き出しがいつもデカイ感じ。でも、時間が流れ続けるアニメで、はたしてそれはお得なのかなって疑問に思うんです。だったら小さなものを拾っておいたほうがいいと。心情をモノローグで語ったりするのも好きじゃないので、なんとなく会話で感じとれるようにすることが、いちばんいいことでしょう。そうした意識は、スレ違いばかりの第1シーズンより第2シーズンのほうが顕著に出ると思います。
映画を観まくった少年時代
――さて、残った時間で子どものころ夢中になった作品や、業界に入ることになったきっかけなどをうかがっていきたいと思います。
- 松尾
- 子ども時代は、アニメよりもマンガのほうが多かったですね。作品だと『サイボーグ009』や『パーマン』になります。あとは『ドカベン』、『銀河鉄道999』かな。その辺をひたすら読んでましたが、それがアニメになったやつはむしろ嫌いでした。
――その理由は?
- 松尾
- プラスアルファの面白さが何もない。「これが動いている姿が見たい」という欲求と「もうひとつ何か違うものを」という期待があったと思うんです。たとえば『009』がアニメ化されると聞いたとき、「まったく違った話が見られるのかな」と思って見たら、案外そうでもなかったりする。むしろ新しい話が多い『ルパン三世』がいいなと。
――ストーリー的にオリジナルがいいということですか?
- 松尾
- 初めて接するストーリーのほうがドキドキしますよね。ルパンの映画なら、最初の『マモー編』のほうで、『カリオストロの城』は「ルパンってこんなんだっけ?」と思ってしまい、当時は大嫌いでした(笑)。原作のルパンって荒っぽかったり、けっこう悪いヤツじゃないですか。
――平気で人を殺しますよね。
- 松尾
- そうそう。そういうのを、子どもがちょっと背伸びして見るのが快感でした。なのに「みんないい人になっちゃってるぞ」って。業界に入ってから、あまりに周囲が「良かった良かった」というから、20代半ばぐらいになってようやく見返したら、「よくできてるなー」って(笑)。
――TVより映画をよくご覧になってたんでしょうか。
- 松尾
- 地元の岐阜市の柳ヶ瀬っていう商店街に映画館がたくさんあって、最大9館ぐらいあったんです。そのうち1館は昔の映画を安くかけてたりして、母親と日曜日に買い物に行くと、映画館に入れておかれたんですよね。それで映画をたくさん観るようになったんだけど、たまに見るアニメの映画は好きじゃなかったんです。そういう中に「これは面白いけど、なんだか途中で終わっちゃったぞ」ってのがあって、それが『機動戦士ガンダム』でした。なので、入り口はTV版より劇場版です。それから再放送をちゃんと見ようと思いました。でも、仕事でガンダムを作りたいとはぜんぜん思ってなくて、むしろ『パーマン』をやりたかったんです。
――その『パーマン』にこだわった理由は?
- 松尾
- 怖い話が好きだったから。『サイボーグ009』も「人が生きている限り、ブラックゴーストはなくならないんだ」ってのを突きつけますよね。『パーマン』だとバードマンがすごく怖い。正義のヒーローのいちばんエライ人なのに、無理難題の指令ばかり押しつけて、しかも失敗すると動物に変えられちゃう。なんなんだって、そういうオトナがいるのが面白いなと思ったんです。自分が活躍する間、代理をしているコピーロボットも頼りなくて、大丈夫かなって。そういうのが超怖くて、すごく好きだったんです。
――それで演出になられたきっかけは?
- 松尾
- 制作進行をやってたんですが、車の運転に問題があって演助(演出助手)になりました。普通はそこから演出やってから絵コンテ描くという順番ですが、「話が面白いからコンテ描いてみてよ」ってたまたま振ってくれる方がいたんです。そのときとにかく絵を描くのが大変だなと。カット割りやカメラワークは映画好きだったからなんとなくできるけど、これじゃ全然進まないって分かってから、絵の勉強をし始める順番でした(笑)。
――コンテの絵は、ふつうの絵と違ってまた特別ですよね。
- 松尾
- 高校のとき建築科だったんです。親の跡を継ぐつもりで工業高校に通ってて、平面図や見取り図、それに設計は毎週やってました。完成予想図をつくるときに三点透視のパースを使うので、理解していたんです。それと部屋の中のサイズが分かる。「アニメって部屋がすごく広くておかしいな」って感じてて、業界入ってからけっこう役に立ちましたね。ひょっとしたら「空間づくり」で評価される理由はそれかもしれません。
――話が前後しますが、そもそもアニメ制作会社に入った理由は?
- 松尾
- バブル期でしたから、仕事はなんでも選べたんです。「カタカナ職業」にあこがれて、片っ端からやってみて良さそうなのを選ぼう、なんて格好つけてたんです。アニメ業界も「映像って格好いいじゃん」なんて、その程度のよこしまな考え方でした。マンガもたくさん読んでたし映画もたくさん観てるし、演出なら絵も描かなくてすむし、イケるんじゃないって。そうしたら演出も絵が描けないといけないし、バブルが崩壊して逃げ場もなくなり(笑)。
――演出の勉強はどういうふうにされたのでしょうか?
- 松尾
- 今しか聞けないと思って分からないことは片っ端から聞いていましたね。『ロードス島戦記』という作品で、遠藤卓司さんという演出チーフについて、シートの書き方などテクニカルなところは全部教えてもらいました。僕が仕事できているのは、遠藤さんに教わったおかげです。僕はあの人の仕事が大好きで、あの人ならではの処理がたくさんあるんです。アナログ時代はマッドハウスでしか撮れないオーラ光があったんですが、あれも遠藤さんの発明なんです。虫プロ時代から引き継いで使われていなかった波ガラス(透過光用の歪んだガラス)を見つけ、こういうマスクを使って3コマ打ちで撮影するとこうなる、みたいに実験を突きつめて開発したんです。
――遠藤さんは映画『 WXIII 機動警察パトレイバー』のトークショーでご一緒しましたが、やはり演出処理のすごい方という印象で残念なことをしました(2009年に物故)。
- 松尾
- 遠藤さんとの会話の中で、自分はコンテがもっとも重要だと再認識したんです。TVシリーズでもかなりの数のコンテを描いているのは、それもあるんですよね。
カメラが対象を撮っている感覚
――演出をやり始めて面白かったことは何ですか?
- 松尾
- やっぱり今さんと会ったときでしょうね。『ジョジョの奇妙な冒険』(1994年のOVA版「Adventure12」)で「漫画家が演出やるけど処理が分からないから手伝って」って言われて、「へー、最近は漫画家自身がアニメもやるんだ」と、すっかり勘違いしてたんです。それで絵コンテを見たら、「あ、原作者じゃないんだ」って(笑)。今さんは「実写で撮るならこういう風になる」みたいなことを、すごく積極的にやろうとしてました。たとえば「望遠で撮れば背景はすごく速く動くはずだ」と。アニメってリアルなスピードではなく、気持ちいいスピードに落ち着いていた部分があるんです。撮影台のギアが0.25ミリ単位で動くから、その半分か倍数の引きスピードを標準的に決めて、その中からシーンに合ったのを選ぶようなところがあったんですね。
それでアニメってふだんは速すぎるよねって。それなのに速くしなければならないときは遅い。それが今さんは気に入らないから、空間の奥行きを計って移動をやりたいんだと。あのときに演出上で実写のカメラの振れ方をお互いたくさん研究しました。次の『パーフェクトブルー』(97)に入ったときにはパソコンが使えるようになったので、いろいろシミュレーションもしたし、お互いビデオカメラを買って実験もしました。どういうカメラを選ぶのか、それをどこに置くのか、どういう画角で切りとるといいのか、そんな話をたくさんしたので、演出としてはあの時代がいちばん楽しかったです。あのころの知識や経験が、その後相当生きています。
――松尾さんの演出はひと味違うなって、そう思った秘密が腑に落ちた感じです。誰かがカメラ持ってる感があったので。
- 松尾
- それは嬉しいですね。でも、富野さんには「だからお前は人の心にカメラが入っていかないんだよな」って言われてて、それは自覚してることなんですよね。どこか客観視している。それは舞台の影響があるのかもしれません。お客さんの立場では、人のスレ違いや交わりみたいなのは舞台がいちばん面白いなと。だから自分で表現したいと思ったとき、どうしても舞台が出てくるんでしょう。それとカメラが好きなので、「やっぱりこういうアングルで撮ったほうが落ち着く」「こういうときに驚くんだ」「こういう画面の変化があれば、何かが起きる予感がする」って、あのころたくさん勉強したんです。その分、人の心に入っていくことが後回しになったのかもしれません。
――今回は『 サンダーボルト』のクールさに合ってるかもしれませんね。この内容で心に入ったら過剰かもしれないし。
- 松尾
- そういう意味では、戦争が少しは俯瞰に見えていいかもしれませんね。僕は『ユナイテッド93』って映画の臨場感がすごく好きなんです。ポール・グリーングラス監督はドキュメンタリー出身なんですが、ものすごい完成形の映画を初めて見たなと。それまでのドキュメンタリータッチって映画になっていないと感じていたのに、『ユナイテッド93』はちゃんと映画になっている。その後の『ボーンシリーズ』も含めて、だいぶ研究しました。ドキュメンタリーは当事者にカメラ近づけるわけにはいかないから、根詰めて何か話しているとき、望遠で撮るんですよね。その「盗み撮り」みたいな感じが、「この2人はよろしくないことをやっている」あるいは「重要なことを決めようとしてる」みたいな臨場感につながる。そんなドキュメンタリーが持ってる強みを映画にしている感じが、すごく気に入って、大好きです。
――なるほど。もう一度、そういう目で『 サンダーボルト』を見てみる楽しみもありそうですね。どうもありがとうございました。
PROFILE
|
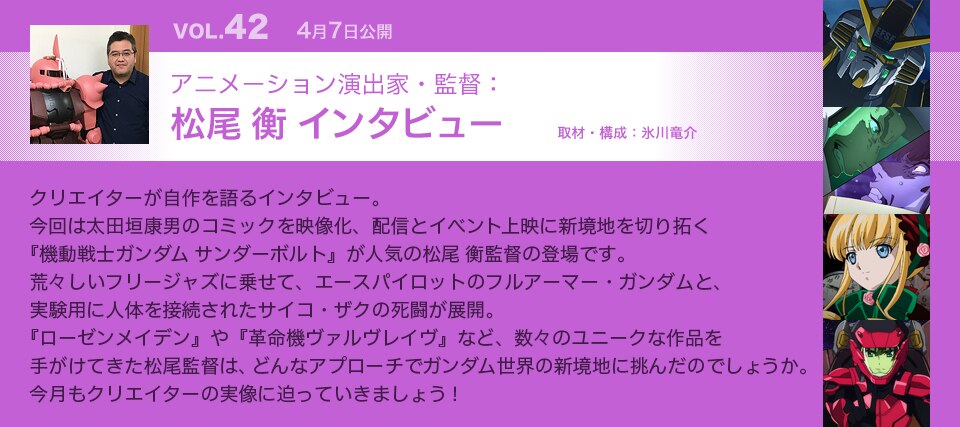
 松尾 衡(まつお・こう)
松尾 衡(まつお・こう)















