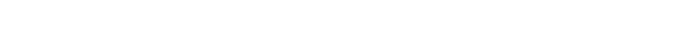業界著名人がアニメ作品をオススメ!
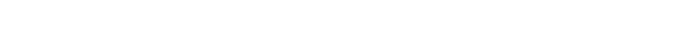
冷や汗タラリ、回転して変身する魔法少女、流れ続ける幸せな音楽。業界標準的ツールの多くの創始者で、サトジュンの愛称で知られる佐藤順一監督。その作品歴からアニメ演出の奥深さが語られます。
 監督:佐藤 順一 インタビュー
監督:佐藤 順一 インタビュー
取材・構成:氷川竜介
クリエイター感覚で、アニメのツボを徹底的に刺激!自作にまつわる貴重なエピソードから、
子どもの頃に大好きだったアニメ、プロを目指すきっかけとなった衝撃の作品などなど、
魅力的なガイダンスを聞きだします!
原点となったアニメ体験の思い出を交えつつ、クリエイターが自身と自作を振り返る好評連載。今回は最新作『 M3~ソノ黒キ鋼~』でダークなロボットアニメに挑戦するベテラン監督・佐藤順一さんにお話をうかがいます。
東映動画に所属していた時期、児童向け作品のシリーズディレクターを歴任し、『美少女戦士セーラームーン』や『おジャ魔女どれみ』など長期人気作品の第1シリーズを立ち上げたその実力は、独立後も数々の作品で発揮されていきます。そして佐藤順一監督が始めたことは、他の多くの作品に受け継がれて、スタンダード化していく。影響度で言えば屈指のものがあります。
ポジティブで優しく感動的な作風は、どういう視点から生まれたのか。そしてその印象とは正反対にも思える『 M3』では何に挑戦しようとしているのか。今月も、ツボをいっしょに探っていきましょう!
子ども向けアニメの面白さにめざめた原体験
――まず、視聴者としてアニメをご覧になった子ども時代のお話からうかがえますか?
- 佐藤
-
小中学生のころは「アニメ好き」というほどではなかったですね。見ていたのは東京ムービー(現:トムス・エンタテインメント)の『侍ジャイアンツ』(71)や『ど根性ガエル』(72)ぐらいで、むしろ『太陽にほえろ!』(72)などの刑事ドラマが好きでした。映画自体も家族で行く習慣がなくて、ゴジラシリーズの同時上映で『パンダコパンダ』(72)を観た程度です。
――それが、なぜアニメ業界をめざそうということに?
- 佐藤
-
高校生のころ、なつかしいアニメーションのオープニングを流す特番があって、ビデオのない時代ですから、『鉄人28号』(63)や『エイトマン』(63)、『狼少年ケン』(63)などを子どもの時以来に観たんです。鉄人のカゲが歩道を歩いてくるところとかフラッシュライトの中に立つエイトマンとか、頭の中では格好いい映像だったのに、古い作品ですから思った以上にショボイわけですよ(笑)。それで最初はガッカリしたんですが、そのうち胸の中にじわーっと来るものがあり、泣けてきたので驚きました。つまりそれって子どものころの記憶なんです。友情や正義感、あるいは「こういうときは嬉しいよね」とか「こんな悪いやつは腹が立つよね」とか、そういうものをアニメからたくさんいただいていたことに気づいたんです。子どもだから物語は忘れるわけですが、そのとき体験した感覚は肥やしみたいに土壌にしみこみ、ずっと記憶の中に残る。それで「子ども向けのアニメづくりって、ものすごく面白い仕事かもしれない」と、興味を抱いたわけです。
――その後の作品歴を考えると、納得ですね。それで制作現場にはどうやってたどりついたのでしょうか?
- 佐藤
-
『宇宙戦艦ヤマト(劇場版)』(77)がヒットしたおかげで裏側にあった制作情報が雑誌などで入るようになり、それに背中を押されました。子ども向けをやりたいという想いが当初から強かったので、他の会社よりも作家的なカラーがないように思えた東映動画(現:東映アニメーション)に試験を受け、日本大学藝術学部映画学科アニメーションコースを中退して演出で入ります(1981年入社)。
――最初から演出志望ですか?
- 佐藤
-
演出は大学で学んでいましたから。絵を描くことは好きですが、自分でアニメのキャラクターを描いても似ないんですよ(笑)。それで東映に入ったら、先輩の演出家たちの大半がアニメが好きで入ったのではないという事実に驚きました。ほとんど京都の撮影所からの配置転換でTVアニメに来た実写出身の方たちで、誰も絵が描けない(笑)。
――それは東映動画の初期TVアニメの特徴のひとつですよね。東映時代を総括してみて、手応えはいかがでしたか?
- 佐藤
-
いちばん大きい財産になったのは、子ども向けをガッツリやれたことです。シリーズディレクターとしてプロデューサーといっしょに玩具メーカーに出向き、企画の人も交えながらデザインとアニメの内容について協議して決めるという経験もできました。商業ベースのアニメをつくるやり方や、何ができて何ができないかなど、東映で学んだことは多いですね。一般的なアニメではマーケティングをしないと思いますが、子ども向けの玩具ビジネスは徹底してやります。女の子に「いちばんなりたい職業は?」「いまどこに行きたい?」など、ものすごいリサーチをかける。ベテラン演出家もアニメ好きではない人たちですから、「子どもってこういうの喜ぶよね」と同じ目線で作っている。「主人公はここでがんばる」「こうやって笑わせる」「悪いやつはひどい目にあう」みたいな作り方を、きちんと押さえてやるわけです。これは東映の良さだと思っていて、それが自分にも合っていたということなんですね。
使いやすいパーツやツールの開発
――その東映時代、佐藤順一監督は『きんぎょ注意報!』(91)や『美少女戦士セーラームーン』(92)『おジャ魔女どれみ』(99)など画期的な作品のシリーズディレクターをいくつも担当されています。
- 佐藤
-
作品は自分で選ぶわけじゃないので、たまたまですよ。
――でも、そこで監督が始めたいろんな表現が今や海外でも使われてるようになっています。中国出張で見たTVアニメでも「冷や汗タラリ」とか「いきなり二等身キャラになる」とかやっていたので、もはや国際的なスタンダードになっていますね。
- 佐藤
-
自分ではそんなすごいことをやっている意識はないんですが、確かにそうしたことも東映で学んだことのひとつです。東映は各話の演出が他社で言う監督に近いため、シリーズディレクターは演出のコンテを認めるべきという空気があるんです。とはいえ作品のテイストは統一しなければならない。そこで「これとこれを組み合わせると、この作品になります」というパーツやツールを決めるんです。『きんぎょ注意報!』はその典型で、「わぴこがいれば頭に猫を乗せる」とか「冷や汗をタラリと流せばいい」とか、誰でもコピーできるツールをいっぱい用意しました。開発したのは主に原作者の猫部ねこさんですけど、そうしないとシリーズの色が出ないんです。でも「誰でも使えるように」というのが目的ですから、よほど使い勝手が良かったということですね(笑)。
――東映は特撮でもシリーズの1~2話は「パイロット」と呼ばれ、全体の方向性やお約束を決めるものとされていると聞きました。
- 佐藤
-
僕も1~2話のコンテはシリーズディレクターが切ったほうがいいと思ってます。1話は登場編だったりするので、2話までやると日常編も含めてパターンが見える。そこまで決めこんでから各話の演出に回すという進め方です。
――他にも監督が始めて広まり定着していった表現には、戦闘魔法少女の変身シーンがあります。『セーラームーン』で、くるくるっと回って足がアップになり、ピキーンとエフェクトが出て変わる演出も、今やスタンダードです。
- 佐藤
-
あれも毎回の尺を稼ごうと努力した結果ですよ。実はロボットものが元ネタでして、『(超電磁ロボ)コン・バトラーV』が好きだったので、合体BANKで「手だけ」「足首だけ」みたいにパーツをアップで見せつつ、「ガシーン!」と合体していくのを思い出して採り入れました。変身中に歌が流れるのも、ロボットものの応用ですよ(笑)。
初のオリジナル作品『魔法使いTai!』の手応え
――さて作品数が多いので、代表的なものに絞ってうかがいたいと思います。まず最初のオリジナル作品『魔法使いTai!』(96)ですが、そのきっかけは?
- 佐藤
-
 自分から手をあげたわけではなく、「OVAやらない?」という話を制作会社とメーカーさんからいただいたので、「これでどうでしょうか?」と差し出してみた感じです。「オモチャを売るアニメーション」ではなく「商品としてつくるアニメーション」という経験したことのない方向性と意味を、ここで学んだんだと思います。『セーラームーン』の直後だったので、「魔法少女で戦う」と「メカと美少女は出す」というオーダーがあり、それでツリガネを出しました(笑)。キャラクターデザイナーと総作画監督には伊藤郁子さんに入ってもらえたのは大きかったですね。「ちょっとエッチぽく」とも言われたので、「分かりました!」とがんばってはみたものの、当時幼稚園だった自分の子どもとその友だちがものすごく喜んで何度も観る作品になりました(笑)。
自分から手をあげたわけではなく、「OVAやらない?」という話を制作会社とメーカーさんからいただいたので、「これでどうでしょうか?」と差し出してみた感じです。「オモチャを売るアニメーション」ではなく「商品としてつくるアニメーション」という経験したことのない方向性と意味を、ここで学んだんだと思います。『セーラームーン』の直後だったので、「魔法少女で戦う」と「メカと美少女は出す」というオーダーがあり、それでツリガネを出しました(笑)。キャラクターデザイナーと総作画監督には伊藤郁子さんに入ってもらえたのは大きかったですね。「ちょっとエッチぽく」とも言われたので、「分かりました!」とがんばってはみたものの、当時幼稚園だった自分の子どもとその友だちがものすごく喜んで何度も観る作品になりました(笑)。
――やはり子どもに届くものがあるわけですね(笑)。初の東映以外の作品でしたが。
- 佐藤
-
やはり違いは大きいと感じました。特に「監督にここまで任すんだ」という驚きです。東映だと脚本や音楽など人選はプロデューサーの仕事で、演出家は素材をもらった上でどう料理するかが仕事でした。ところがいちいち「誰にします、監督?」って聞かれたので、「えっ、僕が決めていいの?」というのにビックリです。
――TVシリーズにもなった人気作品です。
- 佐藤
-
自分としてはOVAの方が印象深いですね。東映では「1年かけてどう見せるか」という経験を積みましたが、これは6本で着地させなければならない。何をどう見せるか詰めるために、コンテを全部自分でやることにした結果、非常に遅れてご迷惑をおかけしました。ただ小中千昭さんに書いてもらったシナリオは伊藤郁子さんとも感性が近い感じもしましたし、とにかく作画のパワーが大きい作品ですね。コンテには必ず何かプラスアルファしなくてはと、伊藤郁子さんががんばってますから、ぜひそこを見てほしいです。ラストに至っては「こうじゃない!」って‘伊藤さんリテイク’が出たほどで(笑)、何度も直しました。あんな風に作画と演出家がキャッチボールできる機会は、なかなかないと思うし、その点でも幸福なシリーズでした。
|